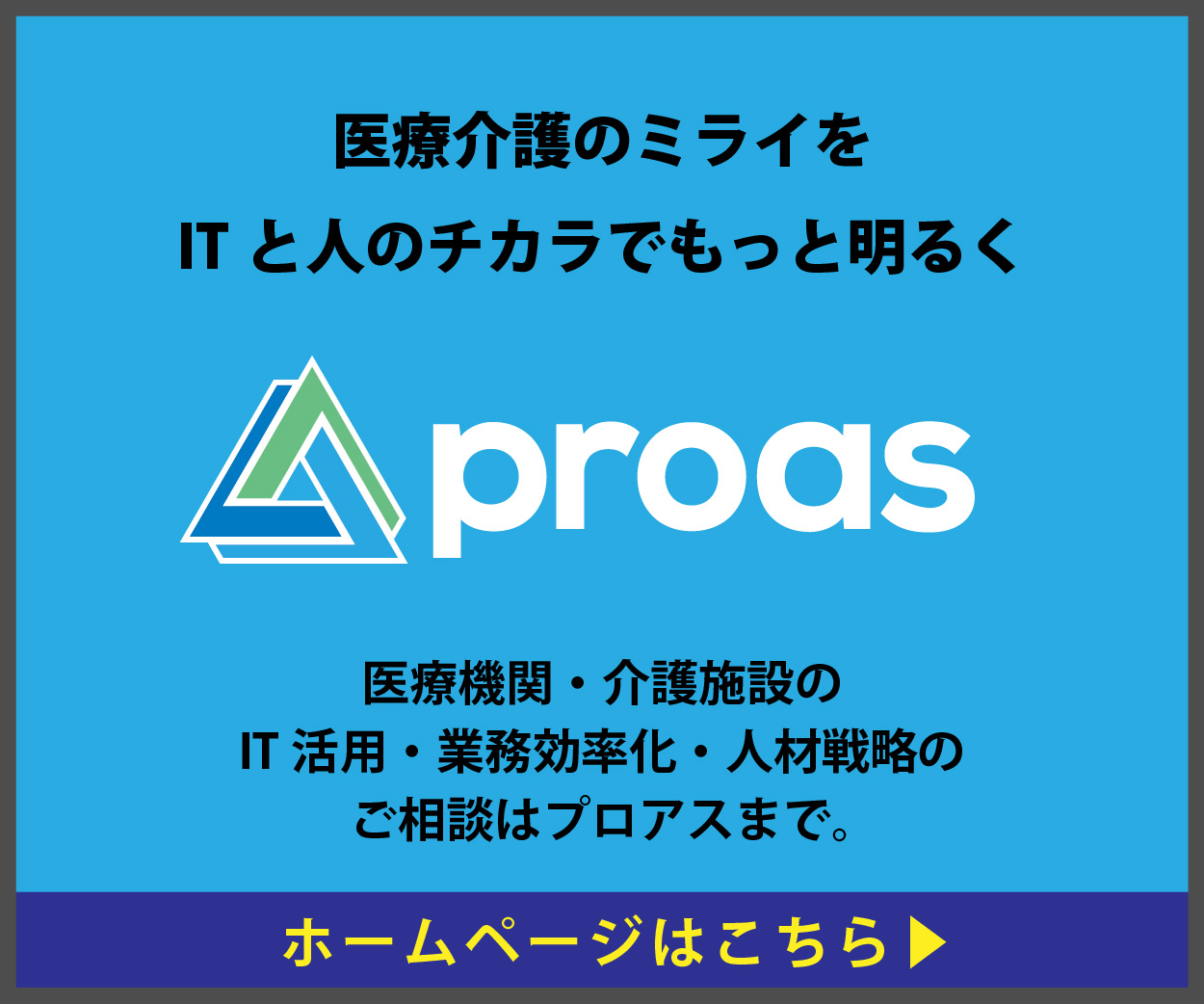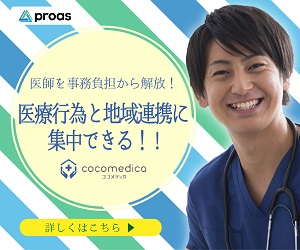病院における「物」とはいったいどのような種類があるのでしょうか?
医薬品、医療材料、医療機器、滅菌器材、医療ガス、リネン、ベット、給食材料、日用品、文具・印刷物…等多岐にわたります。
これらの在庫を適正に管理できていますか?毎月の廃棄数は把握できていますか?
『コスト管理型経営』を実現するための一つに物品管理システムがあります。
今回は大規模病院だけじゃない、中小規模病院も取り組むべき院内の物流管理についてご説明します。
病院内の物流システムとは?
先に述べたように、病院内では医薬品・医療材料のほかにも、治療や診断に要するさまざまな「物」が使用されています。在庫切れが無く、使いたいときに使えることが必須となりますが、過剰在庫を抱え期限切れになる等、廃棄となってしまったものは病院にとって大きな損失となります。
そのため、「適切な時期に適切なものを適切な量」確保することが必要になり、それを管理するのが、病院内の物流システム SPD(Supply Processing and Distribution)です。
☑ 総費用に占める材料比率は適正ですか
☑ 昔ながらの属人的な感覚で在庫管理をしていませんか
☑ 医療スタッフが各部署の物品管理をしていませんか
☑ 経験に頼った発注で過剰発注や発注漏れは起きていませんか
☑ 償還材料は漏れなく保険請求できていますか
☑ 過剰在庫で有効期限切れ。。。廃棄ロスが多くありませんか
☑ 漫然とした在庫管理しか出来ず蓄積されるデータの有効活用は出来ていますか
この中でひとつでも「あるある」と思われた方、今の管理体制を見直すべきです!
病院内の物流システム SPDの意義・目的とは?
ではこのSPDを導入することで、どんな効果が得られるのでしょうか?
SPD導入で実現できる5つのメリットについてご説明します。
①在庫量の削減と請求漏れの防止
⇒購入から使用に至るまでの管理を行い、在庫量の削減や請求漏れを予防することが可能
②搬送の体系化
⇒院内物流全体を組織的に把握した上で、物品の定数化や供給システムを確立し搬送の体系化をはかることが可能
③院内動線の確立
⇒供給部門と使用部門の「物」の動線を総合的に整理することにより「人」「物」の動線を明確に区分し、院内全体の動線計画を確立することが可能
④供給部門の意識改革
⇒部門の機能や責任体制を明確にすることで、職員の意識改革や職場環境の改善が可能
⑤使用部門の労力軽減
⇒供給体制の確立により、使用部門側の在庫管理や物品請求及び搬送に関する業務を軽減することが可能
運用方法の違いから見る病院内の物流管理
病院での物流管理の運用として考えられるのが
①システム化せず伝票運用
②委託業者へ依頼
③病院内でシステム運用
の3パターンに分類されます。
皆さんの病院ではどの運用に当てはまるでしょうか?
では、それぞれに運用のメリット・デメリットがありますので、しっかり理解しましょう。
①システム化せず伝票運用
<メリット>
・システムや委託費用のコストがかからない
<デメリット>
・医療スタッフが行う部署ごとの在庫管理
・経験に頼った発注業務
手書き伝票による記入では、文字の判断に時間がかかったり伝達漏れが発生し、最終的には保険請求漏れとなることも考えられます。また、発注は一担当者の裁量に任され、適正在庫の設定が曖昧で、過剰在庫や期限切れ製品を多く抱えている可能性もあります。
②委託業者へ依頼
<メリット>
・人材確保、労務管理が軽減。委託費用として定量化が可能
・システム費用に関して委託業者持込による負担軽減
・導入時の単価低減効果大
・在庫一元管理、定数化の徹底により在庫低減
<デメリット>
・委託業者任せとなり、院内の人材が育たない
・院内でのマスタ情報や蓄積した各種情報が残らない
・単価低減効果は数年で効果が出なくなる可能性大
・委託費用の負担有
・自院の単価情報を利用され、業者にとっての旨味だけ取られる可能性有
委託費用として、月額100~300万かかることもあり、主に大病院が導入対象となっています。委託当初は効果が出るものの、数年経過後は委託費用に疑問を感じられることもあるようです。
③病院内でシステム運用
<メリット>
・人材の育成、質向上、底上げが可能
・システムを自院で保持・蓄積するため、各種情報が資産となる
・人材の質向上により永続的な単価交渉を実現できる可能性大
・在庫一元管理、定数化の徹底により在庫低減
<デメリット>
・院内で人材を確保する必要があり、人件費用が発生
・システム機器購入費用が発生
物流システムはこれまで大病院でないとなかなか手が出せない。。。といった価格帯のシステムでしたが、近年中小規模病院を対象とした物流システムも販売されるようになってきました。
まとめ
いかがでしたか?
発注業務等、病院内の物流管理をされていない病院はまずないと思いますが、運用方法によりその差は歴然です。これからは、業者任せにするのではなく、自院で物流管理をする時代がやってくるのではないでしょうか?
次回は、院内でシステム運用された事例についてご紹介させていただきます。